 投資家コーギー
投資家コーギー管理者プロフィール
投資歴5年 投資家コーギー ほたて
目標2035年までに資産5000万円、年間配当金収入100万円
(※2025年3月時点で年間配当金予想 約28万円)
インデックス投資(約46%)日本株(約48%)米国株(約6%)の比率で保有中
簿記3級勉強中 目標〜5月までに取得
保有する全銘柄公開中
https://toushikacorgi.com/2025/02/27/理想追求!投資家コーギーほたての「資産ポート/
簿記とは何?
簿記とはお金の流れを記録し、管理するための技術になります。企業や個人資産、負債、資本、収益、費用を帳簿に整理して記録するルールや方法のことを指します。簿記を理解すると、財務状況や経営状態を把握することができます。資格としては「日商簿記3級」「日商簿記2級」「日商簿記1級」があり、3級は初心者向けで、基本的な仕訳や帳簿作成を学びます。2級は商業簿記に加え、工業簿記も学びます。1級では高度な会計知識を必要とし、一般的に税理士や公認会計士を目指す人が学びます。副業で青色申告(税制優遇)をする際も簿記の知識が役立ちますので、副業を考えている人はぜひ学んでいきましょう。
| 日商簿記3級 | 初心者向け。基本的な仕訳や帳簿作成。 |
| 日商簿記2級 | 商業簿記(商業活動に関連するお金の流れなど)や工業簿記(製造業の原価計算など)の知識が必要。 |
| 日商簿記1級 | 高度な会計知識が必要。税理士や公認会計士など専門職を目指す人が目指す。 |
| 日商簿記3級 | 日商簿記2級 | 日商簿記1級 |
|---|---|---|
| 初心者向け。基本的な仕訳や帳簿作成。 | 商業簿記(商業活動に関連するお金の流れなど)や 工業簿記(製造業の原価計算など)の知識が必要。 | 高度な会計知識が必要。税理士や公認会計士など 専門職を目指す人が受けることが多い。 |
| 学習時間50〜100時間程度 | 学習時間150〜300時間程度 | 学習時間500〜1000時間程度 |
| 合格率40〜50% | 合格率20〜30% | 合格率10%程度 |



簿記は副業などを行う時にも必要だし、個別株をやる時も決算書を読む際は簿記の知識があるとスムーズに理解ができるよ!お金の世界の「あいうえお」だね!
簿記の流れについて
簿記の大まかな流れは、「取引の発生」→「仕訳をする」→「総勘定元帳(そうかんじょうもとちょう)に転記する」→「試算表を作成する」→「決算整理をする」→「損益計算表(そんえきけいさんひょう)、貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)を作成する」→「帳簿(勘定)を締め切る」の流れになります。「取引の発生」〜「総勘定元帳に転記する」までは、日々やることになり、「試算表を作成する」〜「帳簿(勘定)を締め切る」までは。決算(年一回)でやることになります。今後、各項目で覚えなければいけない単語が多数出てきますので、大まかな流れは必ず把握していきましょう。


取引の発生を詳しく説明
簿記上の取引とは、企業の「資産」「負債」「資本(純資産)」「費用」「収益」にのいずれかを増減変化をもたらすすべての出来事を指します。これには、「商品の購入や販売」「経費の支払い」「現金の預入」などが含まれ、「借方」と「貸方」の2つの要素に分けられます。帳簿に記録する際には、これらの要素を適切な勘定科目に振り分ける必要があるので覚えておきましょう。取引の種類としては「交換取引」「損益取引」「混合取引」がありますが、基本的に私たちが日常で行う取引を考えていただければ問題ありません。
| 交換取引 | 損益取引 | 混合取引 |
|---|---|---|
| 資産や負債が増減する取引 | 費用や収益が発生する取引 | 交換取引と損益取引が同時に発生する取引 |
| 例:備品の購入する、借入金を返済する | 例:給料を支払う、借入金の利息の支払いをする | 例:有価証券の売却をする、在庫を売却する |



勘定科目(資産、負債、資本(純資産)、費用、収益)への仕訳は今後とても大切になってくるから、必ず覚えてね!これを覚えないと簿記3級には受からないから必須事項だよ!
仕分けをする上で大切なこと
仕分けとは、企業の取引を複式簿記のルールに従って記録する最初のステップになります。取引を「借方(かりかた)」と「貸方(かしかた)」に分けて、どの勘定科目にどれだけの金額を記録するかを決める作業を指します。これが簿記の基本であり、正確な財務諸表(損益計算書や貸借対照表)を作る土台となりますので、必ず覚えておきましょう。
すべての取引は「借方(かりかた)」と「貸方(かしかた)」の2つの側面で記録されます。この金額は必ず一致(貸借一致の原則)します。
例:商品100円を売り上げ、代金を現金で受け取った。(現金(資産)が増え、売上(収益)も増えた。)※「借方と貸方の位置」の図を参照
| 借方(左側) | 貸方(右側) |
|---|---|
| (現金) 100 | (売上) 100 |
勘定科目5つの要素について
勘定科目には「資産」「負債」「資本(純資産)」「収益」「費用」の5つに分けられます。資産とは、現金や売掛金の持っていて嬉しいものを指し、負債は借入金や買掛金など持っていて嬉しくないものを指し、資本(純資産)は資本金などを指し、収益は売上などを指し、費用は仕入れや給料などを指します。
借方と貸方の位置
「資産」「費用」が増えると借方、減ると貸方に分類されます。「負債」「資本(純資産)」「収益」が増えると貸方、減ると借方に分類されます。簿記では書く場所(右側か左側か)も大切な要因の一つであるため、下図を覚えておきましょう。


総勘定元帳に転記する
総勘定元帳とは、企業や個人が行うすべての取引を記録し、勘定科目ごとに集計したものを指します。会計の基本となる帳簿で、仕訳帳から転記されたデータを元に作成され、財務諸表(貸借対照表や損益計算書)などを作成するための重要な資料であります。仕訳帳と総勘定元帳の内容が一致するよう、金額や勘定項目を間違えないようにする「正確性」が大切です。
例:4月1日に銀行から現金100円を借り入れた。(現金「資産」が増えて借入金「負債」が増えた)
| 仕分け | |
|---|---|
| 借方(かりかた) | 貸方(かしかた) |
| (現金) 100 | (借入金) 100 |
↓
| 総勘定元帳 | |
|---|---|
| 現金 | |
| 4/5 借入金(仕訳の相手科目を記入) 100 | |
| 借入金 | |
| 4/5 現金(仕訳の相手科目を記入) 100 | |
決算整理をする
企業や組織が会計期間(通常1年)の終わりに行う作業で、帳簿を正確に占めて財務諸表(貸借対照表や損益計算書)を作成するための重要なステップになります。総勘定元帳の内容を調整し、現実の経済状況を反映させるのが目的です。プロセスとして、「取引の記載漏れや未処理の項目を修正する」「収益や費用を正しい期間に割り当てる(期間損益の適正化)」「資産や負債の評価を見直す」があります。これにより、総勘定元帳のデータをもとに、正確な財務状況と経営成績を把握することができます。主な内容として、「未記帳の取引の処理」「前払費用・未払費用の調整」「収益の繰延べ・未収収益の処理」「減価償却」「貸倒引当金の設定」「棚卸資産の調整」があります。


損益計算書や貸借対照表を作成する
損益計算書や貸借対照表を作成できたらあとは帳簿を締め切るだけ(補助簿などの作成があるが必須ではない)なので、もう少し頑張ってみましょう。
損益計算書とは何
「売上純利益(粗利益)」「営業利益」「経常利益」「税引前当期純利益」「当期純利益」の5つの利益段階を中心に構成されます。
- トレンド分析〜過去数年と比較して、売上や利益がどう推移しているかを見る。
- 利益率〜効率的に儲けているかをチェックする。
- 異常値の確認〜特別利益や損失が大きい場合、その原因を調べる(一時的なものか、構造的な問題か)。
売上総利益(粗利益)
計算式:売上高−売上原価
※売上高〜企業が商品やサービスを売って得た収入で、売上原価を作る・提供するために直接かかったコスト(材料費や製造費など)
→この段階で、企業の本業の儲けの大枠がわかります。
営業利益
計算式:売上総利益−販売費および一般管理費(販管費)
※販管費〜「人件費」「広告費」「事務所の家賃」などが含まれます。
※営業利益〜企業の本業における収益力
経常利益
計算式:営業利益+営業外収益−営業外費用
※営業外収益(利息収入や配当金など)と営業外費用(借入金の利息など)を加味したもの。
→日常的な事業活動全体の利益を示します。
税引前当期純利益
計算式:経常利益+特別利益−特別損失
※特別利益(資産売却益など)や特別損失(災害による損失など)といった臨時的な収支を反映。
→税金を払う前の利益になります。
当期純利益
計算式:税引前当期純利益−法人税等
※最終的に企業がその期間に手元に残した利益で、いわゆる「最終的な儲け」のことを指します。
貸借対照表とは何
バランスシート(B/S)とも呼ばれ、企業のある特定の時点(通常は決算日)での「資産」「負債」「資本(純利益)」の状況を示す財務諸表です。貸借対照表は「その瞬間の財政状況のスナップショット」を提供しており、企業の財務健全性や安定性を判断するのに重要な資料になります。「資産」と「負債+純利益」の2つの部分で構成され、必ず以下の関係が成り立ちます。
- 資産の質〜現金や売掛金が多いと流動性が良いとされます。
- 負債の割合〜負債が資産に対して多いと借金依存性が高い(財務リスクが高い)可能性を確認。
- 自己資本比率〜高いほど財務が安定しているとされる。(目安30パーセント以上が健全)「純資産÷総資産」
- 流動比率〜1以上だと短期的な支払い能力があると判断される。「流動資産÷流動負債」
資産=負債+純利益
※この上記等式がバランスしているため、バランスシートと呼ばれる。
資産(Asset)について
企業が所有する経済的価値のあるもので、流動性(現金化のしやすさ)に応じて分類されます。
- 「流動資産」〜1年以内に現金化できもの(例:現金、預金、売掛金、棚卸資産=在庫)
- 「固定資産」は、1年を超えて使用・保有するもの(有形固定資産〜土地、建物、機械 無形固定資産〜特許権、商標権 その他の資産〜長期預金、子会社株)
負債(Liability)について
企業が他人(銀行や取引先など)に支払う債務。
- 「流動負債」〜1年以内に支払期限が来るもの(例:買掛金、短期借入金、未払費用)
- 「固定負債」〜1年を超えて返済するもの(例:長期借入金、社債)
純資産
負債を除いた、企業の実質的な「自己資本」のこと。
- 「株主資本」〜株主が出資した「資本金」「資本余剰金」「利益余剰金」(過去の利益の積み立て)
- 「その他」〜評価差額(資産の時価評価による差額など)
帳簿(勘定)を締め切る
企業や個人事業主が一定の会計期間(通常は月次、四半期、年度末)の取引記録を整理し、その期間の財務状況や経営成績を確定させる作業を指します。目的とし、「期間損益の確定」「財務状況の確認」「法律遵守」「次期への準備(0からスタート)」があります。税務申告が必要な場合、法人なら決算日から2〜3ヶ月以内(日本では通常5月末まで)に締め切ることが多いため、注意が必要です。基本的には「取引を整理して、結果を確定させる」という作業になり、現代では会計ソフトなどもありますので、活用していきましょう。
まとめ
簿記3級といっても、初めて関わる分野となると知らない単語などもたくさんあり、難しいと感じるかもしれません。ただ、紐解いていくと単純な仕組みであることがわかり、全体像がハッキリと見えてきますので、最後まで諦めずに勉強していきましょう。簿記3級を取得すると、現在働いている企業についてより理解することができ、今まで見えていなかった改善点などが見えてくるようになります。もちろん、自分で事業をする際や副業などにも役立つ知識になりますので、ぜひ簿記の世界に足を踏み入れましょう。著者が購入して勉強した簿記の教材を下のリンクに貼りましたので、一緒に勉強していきましょう。
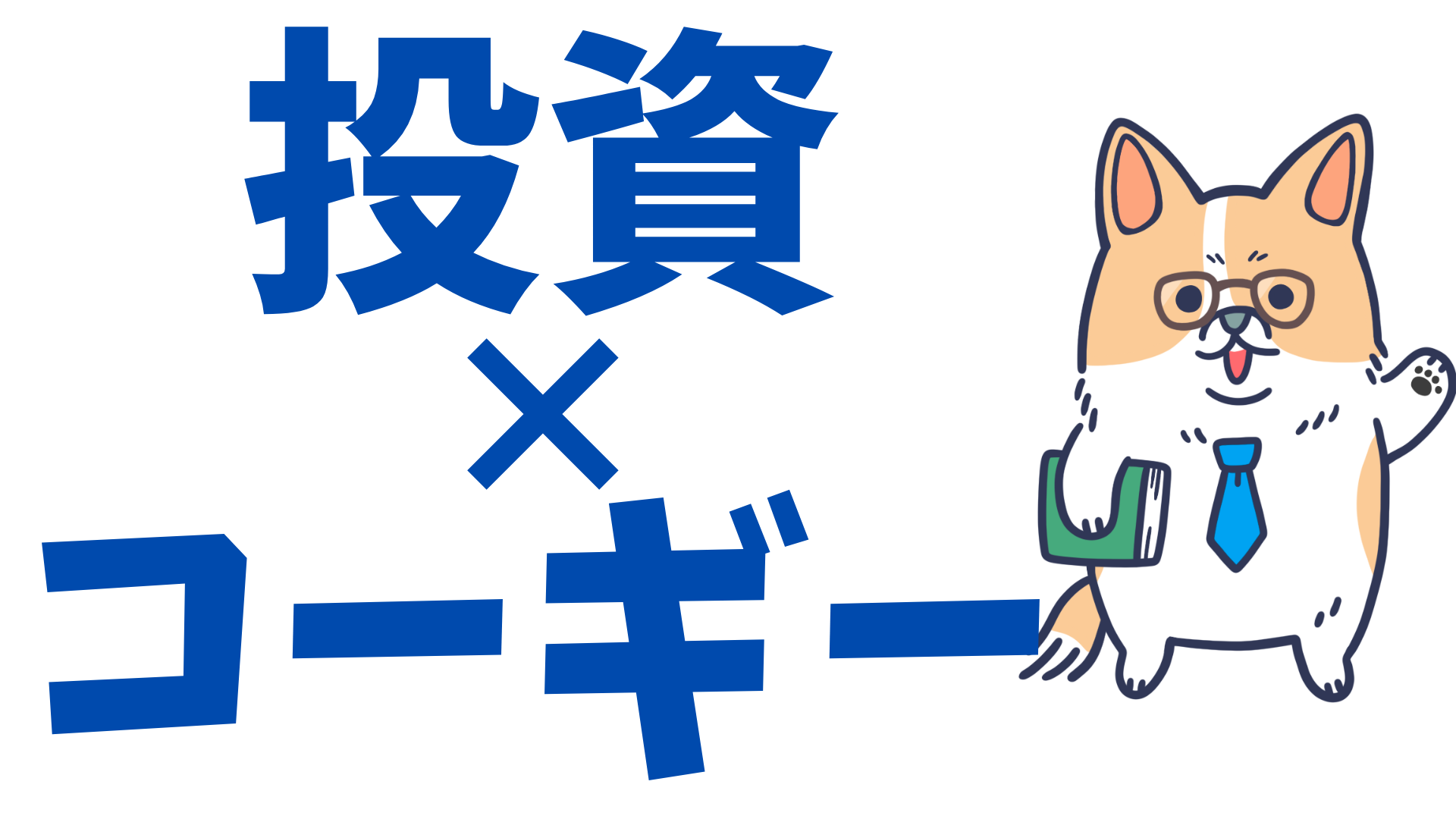

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45cc4fa5.6dbf354c.45cc4fa6.9cf95d0b/?me_id=1285657&item_id=12996320&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F01140%2Fbk4300115761.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45cc4c3f.7a068d58.45cc4c40.4c44bf1e/?me_id=1213310&item_id=20568935&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9969%2F9784820729969_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45cc4fa5.6dbf354c.45cc4fa6.9cf95d0b/?me_id=1285657&item_id=12996446&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F01140%2Fbk4300115796.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)






コメント